「これを読まなければサルである」
この本の帯は、ひどく挑発的である。
しかし、当書で紹介されている必読書を数冊でも読み始めたならば、この帯の意味はPRのための奇をてらった表現ではなく、文字どおりの意味だということを痛感させられる。
自分がいかに無知で、視野が狭く、教養がなく、考えが浅く、とどのつまりサルであるか。
この記事は、私がサルから人間になるための記事です。
さらに人間となっていく過程で、文豪たちの文章をとおして、考える力を磨き、言葉の表現力を蓄えていく所存です。
順に150冊の必読書と向き合い、考えを巡らせ、咀嚼し、感想を添えていきます。
感想といっても、100字ほどの短い感想であっても、150冊分ともなれば15,000字になってしまうため、つぶやき程度の感想にとどめておきます。
- 『必読書150』に挑戦してみたい人
- すでに挑戦している人で、他人の感想を読みたい人
- 150の必読書を読破するための仲間がほしい人
【これまでに読了した必読書の数】
【随時更新】14冊/150冊(※2025年4月現在)
【読了した本】つぶやき感想
【人文社会科学】
プラトン 『饗宴』
哲学とは、知識をひけらかすことでもなく、人よりも知恵で優位に立つことでもなく、物事の本質を捉えるために考えることだと、ソクラテスの芯を食った問いが教えてくれる。
アリストテレス 『詩学』
舞台・映画・ドラマ・小説・漫画・ゲーム・アニメなど、あらゆるエンタメに通じる核をえぐり取った解説本。人はなぜ、悲劇を、カタルシスを求めるのかが種明かしされる。
アウグスティヌス 『告白』
内に、内に、内省を繰り返し、自分の内にいる神と対話しながら、魂を研鑽し、自分なりの答えにたどり着いていくさまは、宗教や信仰に関係なく、人が目指すべき姿だと思う。内省日記を書くきっかけを与えてくれた一冊。
レオナルド・ダ・ヴィンチ『レオナルド・ダ・ヴィンチ手稿』
レオナルドのあくなき探求心と観察眼には、頭が下がる。芸術以外の分野への知識も圧倒的なのに知識をひけらかすことなく、子どものような純粋な好奇心の目をとおして世界を見つめている。
【海外文学】
ザミャーチン 『われら』
ディストピアを描いたフィクションであるはずなのに、日記形式で淡々と綴れる世界はノンフィクションのような没入感があり、なにより不気味だった。
サルトル 『嘔吐』
実存主義の意味を物語をとおして体感できる一冊。主人公が吐き気を起こす理由を真に理解したとき、人間の存在とは何なのか・なぜ我々は生まれてきたのかの一つの答えにたどり着ける。
シェイクスピア 『ハムレット』
脈々と受け継がれている西洋感覚、「メタファー」や「皮肉」や「カタルシス」のエッセンスが詰まっている。
トーマス・マン『魔の山』
独特な時間感覚に襲われ、味わったことのない不思議な読書体験をした。それは主人公のハンス同様、魔の山が放つデカダンスの魅力に閉じ込められていたからかもしれない。デカダンスはどこか居心地が良くて長居してしまう気持ちも頷けるし、新たな気づきを得ても忘却してしまうハンスの行動にも共感できる。物語の最後で、デカダンスから抜け出す方法をハンスが身をもって教えてくれる。
【日本文学】
二葉亭四迷 『浮雲』
高校生のときに暗記しただけの著者名と作品名が、まさかヘタレ主人公のラブコメ恋愛小説だとは思いもしなかった。時代背景は現代と大きく異なるが、親の視点や、男女の視点には今でも変わらない共通点があり、抵抗なく物語に入っていける普遍的小説。
安部公房 『砂の女』
「慣れ」や「惰性」はこわい。意識していたものが、「慣れ」と「惰性」によって、感覚がまひしていき、無意識下へと落ちてゆくこわさは、現代社会にも通じるものがある。
島尾敏雄 『死の棘』
“愛憎”という言葉では片付けられないほどの、いびつな夫婦の形。あまりにいびつ過ぎて傍目から見ると勘違いされそうだが、愛に変わりなかった。
萩原朔太郎 『月に吠える』
感情を表す日本語は無数にある。だが、それで本当に人の感情を的確に表現できているのだろうか。この詩集を読んだあとは、我々が普段使っている感情表現など陳腐で、表現しているとは到底言えなくなってしまう。
正岡子規 『歌よみに与ふる書』
理屈っぽい歌や、当たり前のことが書かれた歌、おおげさで嘘っぱちでしらける歌を、聞き覚えのある百人一首などを例にして、容赦なく批判していくが、そこには説得力があって、読んでいて快い。
円地文子『食卓のない家』
成人した犯罪者の家族は、世間やマスコミに追いかけまわされ、非難され、責任を取らされるべき対象なのだろうか。テロリストの息子に対して、一貫して距離を置き責任を取らない個人主義的な主人公と、家族という一括りで糾弾する世間とのズレ。70~80年代の物語だが、SNSや他メディアによる犯罪者家族への非難が昨今でも続いている日本に恐怖を感じる。
【Connecting the dots】私の身に起きた変化
なんとなく民放の恋愛ドラマを観ていたら、ビビビとくるシーンがあった。
なぜなら、プラトンの『饗宴』の話を引用していたからである。
またあるときは、読んでいたスピリチュアル系の本に、サルトルの名前が出てきた。
サルトルの『嘔吐』を読了していた私は、抽象的で理解し難いとうわさのスピリチュアル本を読了していた。
必読書で読んだ内容や文豪たちが、人生の思わぬ場面で登場してくる。
もし読んでいなかったら、ビビビとくることもなく、思考停止するか、気付くことさえなかっただろう。
点と点が、思いも寄らないところで線へと繋がっていく。
そんな体験をしたものだから、読むのが楽しくてしかたない。
さいごに
150冊すべてを読み終えるのに、何年かかるか分かりません。
吉岡実の詩集があるかと思えば、世界一長い長編小説と称されるプルーストの『失われた時を求めて』もリストに入っています。
それぞれのページ数を度外視して、単純に1カ月に1冊で計算すれば、12年半。
できれば、その半分の6年くらいで読破したいところ。
私と一緒に『必読書150』に記載されている全作品を読破しませんか?

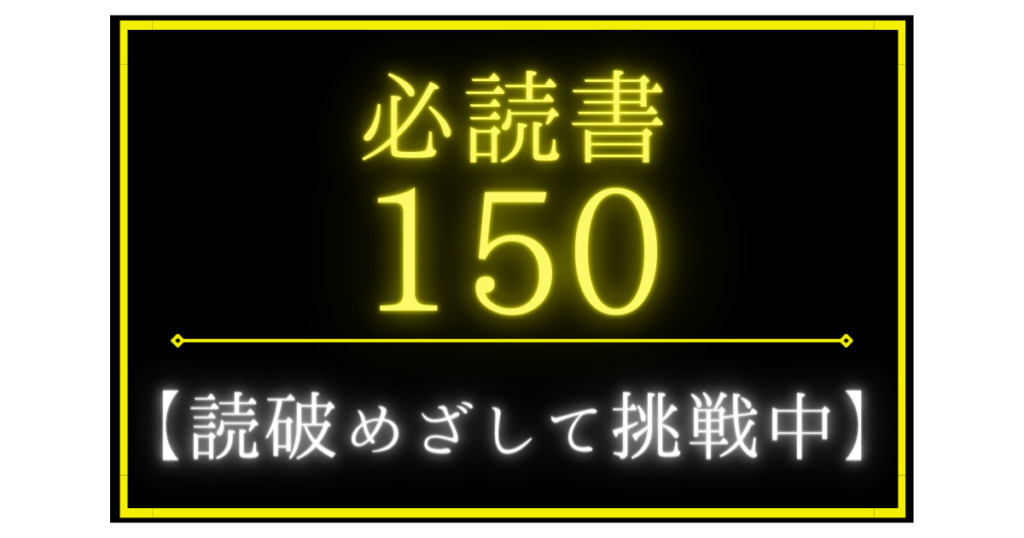

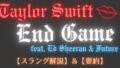

コメント